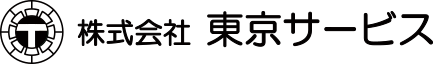【とい】雨樋の役割と素材の特徴とは【初心者向け解説】
2025年 02月14日
こんにちは!
株式会社東京サービスのブログ担当、新人Mです。
弊社は東京都多摩地区を中心に、屋根、外装、軒工事を主体にしている建設会社です。
そこで、本ブログでは、業界未経験のブログ担当が、弊社で行った工事などを例にしながら、屋根工事やその他工事について勉強し、理解した内容を発信していきます。
そのため、屋根工事についての予備知識がない方でもご理解いただける内容になっているかと思います。
今回ご紹介するのは、雨樋の役割と使われる主な素材、そして素材別の特徴についてです。

普段の生活のなかで、雨樋について強く意識することは少ないのではないでしょうか。しかし、雨樋は建物を守るうえで大きな役割を担っています。
雨樋とは何か?その役割は?
雨樋とは、建物の屋根に降った雨、雪等の排水設備のひとつです。「とゆ」、「とよ」とも呼ばれることもあります。
建物の屋根に降った水を効率よく集め、適切に排水する用途で設置されます。
雨樋の主な役割としては、主に以下の3点があります。
建物の基礎を守る
雨樋は、雨水から建物の基礎を守っています。
小さい建物であっても、雨や雪の際には大量の水分が屋根に降り注ぐことになります。
ニュースでよく聞く、「1時間に1㎜の雨」というのは、1㎡あたり約1ℓ以上の雨が降る、ということですので、多くの屋根にはその何倍もの水が建物の屋根に降り注いでいます。

雨樋がなければ、屋根に降った雨は屋根の斜面をすべり落ち、軒下のごく狭い範囲の地面に集中して落ちることになります。そうして落ちた水は、建物の基礎部分の周辺に溜まっていきます。そして、建物の木部を腐らせ、シロアリの発生などにより、建物の耐久性が低下することにつながります。
外壁の保護
雨樋は、外壁を雨水から守り、汚れや劣化を防いでいます。
雨樋がない場合、雨水は屋根から落下した際に泥をはね上げて外壁の汚れの原因となります。加えて、雨水は外壁を伝って流れ落ちていくこともあり、壁面が湿潤状態になることで、外壁の劣化を早める原因となります。特に木造建築では、腐朽やカビの発生を防ぐために雨樋が果たす役割は大きいと言えます。

周辺環境の保護
雨樋は、雨による騒音や足元不良を防止し、建物周囲の環境を守っています。
雨音はときに人々に安らぎをもたらします。しかし、雨樋がない場合、雨水が屋根から地面に落ちる音が鳴り響きます。最近頻発している災害級の大雨の場合などでは、こうした雨音は安らぎを与えるどころか、騒音になってしまうでしょう。
加えて、屋根の雨水が庭に流れ込むことで、水たまりやぬかるみができて歩行が難しくなったり、また庭の景観に悪影響を与えることもあります。雨樋を使って雨水を計画的に排水することで、庭への影響を軽減することが出来ます。
このように、雨樋は建物自体や生活環境を守るうえで多くの役割を果たしていると言えます。
雨樋は何で出来ているのか?
一般に、雨樋の材質には樹脂や金属が使われています。そのうちメジャーなのは、塩化ビニール樹脂(塩ビ)、ガルバリウム鋼板・アルミニウム・銅・ステンレスの5種類です。
塩化ビニール樹脂(塩ビ)

最も一般的なのが塩化ビニール樹脂、いわゆる塩ビ製のものです。塩ビは加工が容易で軽量、かつ安価なため昔から便利に用いられてきました。現在、ホームセンター等で見かける雨樋も、塩ビ製のものが大半を占めています。しかしその一方、塩ビは中長期的な風雨や日光、熱に弱く、耐用年数が比較的短いことが欠点です。そのため、近年各種メーカーはこれらの耐用性を高めたモデルを開発しています。
https://www.eslontimes.com/kenzai/gallery/gallery.html
(雨樋の大手メーカーの一つである積水化学工業様のホームページです。様々な塩ビ製樋の施工事例の画像がご覧いただけ、商品バリエーションの多さがわかります。)
ガルバリウム鋼板
ガルバリウム鋼板を使用した雨樋も各メーカーから出ています。
ガルバリウムとは鋼板に亜鉛とアルミニウムをメッキした合金で、耐久性とコストパフォーマンスのバランスに優れていることから、近年外壁や屋根材などに盛んに用いられています。
一方で、それでも塩ビ製に比べるとコストが高く、またメッキであるためにアルミニウムやステンレスほどの耐久性がないという弱点があります。
アルミニウム
アルミ二ウムはさびにくい上に日光や熱にも強く、塩ビ製やガルバリウム鋼板製に比べても耐用年数が高いのが特徴です。
比較的高価になってしまう欠点はあるものの、その耐久性の高さは折り紙付きです。

弊社ではアルミ雨樋「ストロング・シームレスガター」の施工を行っております。現場成型を行うことで中間ジョイントを排し、見た目の美しさだけでなく水漏れのない高い耐久性を発揮します。
詳しくはこちら
https://satoh.co.jp/tokyoservice/construction/raingutter/
銅
高級感を演出したい場合には銅製の雨樋を使います。
特に神社や仏閣など、和風で重厚感のある建物に多く用いられます。
年月が経つにつれて青銅色に変化し、味わい深い質感を演出してくれる銅製ですが、材料や施工のコストが高く、また経年劣化により腐食し穴が開く等のリスクがあるため、近年ではあまり利用されません。
ステンレス
ステンレスは腐食に強い金属として知られ、雨樋においてはしばしば部材等に利用されます。高い耐久性から、雨樋に利用されることもありますが、高価なことや製品ラインナップが他素材に比べて少ないことから、あまり普及していないようです。
以上が雨樋の主な素材と特徴です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。普段意識しない雨樋ですが、さまざまな役割があり、バリエーションも豊かです。
皆さんのお宅を雨から守る雨樋を、ぜひ一度ご確認してみて下さい。
そして今回の記事が、雨樋について考えるきっかけになれば嬉しいです!
また、雨樋のトラブル等がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。
著者情報
株式会社東京サービス
株式会社東京サービスは東京多摩地域を拠点に、屋根や外壁、雨樋の工事をはじめとした各種工事の施工に携わっている小さな会社です。
国立市で創業70年以上の歴史を持つサトウグループの一員として、地域のお客様の様々なニーズにお応えしています。
本ブログでは、業界未経験の新入社員Mが、屋根工事やその他工事について様々なことを勉強し、わかりやすい解説をモットーに、備忘録的に書き記していきます。
もちろん、掲載に当たっては経験豊富な先輩たちに内容の監修をいただいていますのでご安心下さい♪